2025年10月1日、MicrosoftはWindows 11の最新機能更新プログラムであるバージョン25H2(2025 Update)の一般提供を開始しました。
今回のアップデートは、前バージョンである24H2からの変更は小規模とされていますが、一部でwindows 11バージョン25H2の不具合に関する報告が上がっており、すぐにダウンロードやすべきか、あるいは安定性を重視して更新を待つべきか、判断に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、BluRay・DVD・デジタルTVアプリでの再生障害や、主に企業で利用されるWUSA経由のアップデートが失敗する可能性といった具体的な不具合が公式に確認されています。
また、アップデートは強制定期に更新される?といった疑問や、Windows 10からの無償アップグレード期間が終了した今、アップグレードすべきか慎重に判断したい状況です。
この記事では、現在判明している問題点とその具体的な対処法、そしてあなたのPC環境や利用状況に合わせた最適な判断基準を、深く掘り下げて分かりやすく解説します。
Windows 11 バージョン25H2の不具合情報
- BluRay・DVD・デジタルTVアプリでの再生障害
- WUSA経由のアップデートが失敗する可能性
- その他に報告されている不具合
- バージョン24H2からの変更は小規模
- 今回のアップデート概要
BluRay・DVD・デジタルTVアプリでの再生障害

Windows 11 バージョン25H2へのアップデート後、一部の環境で著作権保護(DRM: Digital Rights Management)が適用されたコンテンツの再生に問題が起きる可能性が報告されています。
この問題はバージョン24H2から継続して確認されているもので、Microsoftの公式なWindowsリリース正常性情報でも既知の問題として掲載されており、25H2でも引き続き注意が必要です。
具体的には、市販のBlu-rayディスクや録画したデジタル放送など、高度なコピーガード技術が使われている映像をPCで再生しようとした際に、コンテンツを再生しようとするとエラーが表示されたり、画面が真っ黒(ブラックアウト)になったり、再生が頻繁に中断されたりする場合があります。
この問題は、映像出力経路を暗号化するHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)を適用する「拡張ビデオ レンダラー(EVR)」という仕組みを使用する、比較的古いサードパーティ製再生アプリで発生する可能性が高いとされています。
一方で、YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoといった主要なオンラインストリーミングサービスは、ブラウザや専用アプリ内で独自の再生・保護技術を使用しているため、この問題の影響は受けないとされています。
Microsoftはこの問題を正式に認識しており、現在修正対応を進めている状況です。
日常的にPCで物理メディアの映画を鑑賞したり、テレビ番組の録画を再生したりする方は、修正パッチが提供されるまでアップデートを少し見合わせた方が賢明かもしれません。
再生障害のポイント
影響を受ける可能性のあるアプリ: 著作権保護(DRM/HDCP)を利用する一部のBlu-ray/DVD/デジタルTV再生ソフト
主な症状: 著作権保護エラー、再生中断、フリーズ、ブラックスクリーン
技術的背景: 拡張ビデオ レンダラー(EVR)に関連する問題の可能性
現在の状況: Microsoftが問題を調査中であり、将来の月例更新プログラムなどで修正される見込みです。(出典:Microsoft Windows サポート)
WUSA経由のアップデートが失敗する可能性
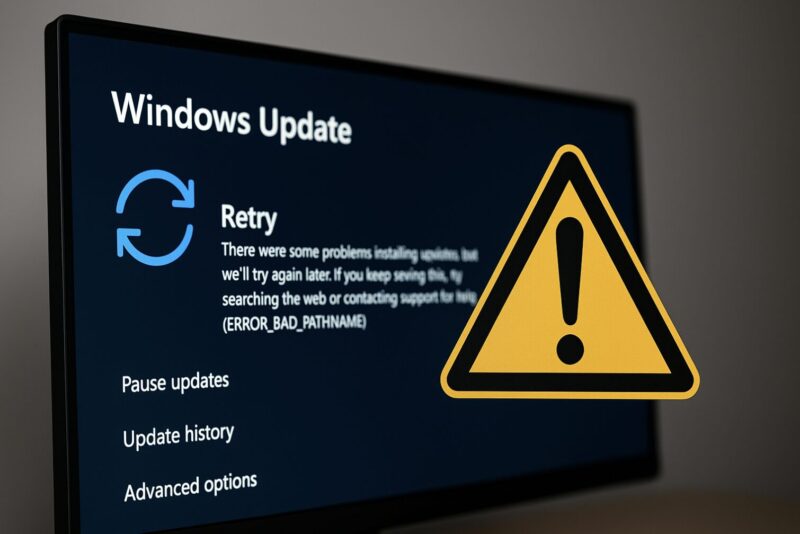
次に、主に企業のIT管理者などが利用するシナリオで発生する問題ですが、Windows Update スタンドアロン インストーラー(WUSA.exe)を利用したアップデートに関する不具合が報告されています。
これは、個人ユーザーが家庭でPCを使う上では、まず遭遇することのない特殊なケースです。
この問題は、複数の更新プログラム(拡張子が「.msu」のファイル)がまとめて保存されている社内ネットワークの共有フォルダから、特定の.msuファイルを直接ダブルクリックで実行したり、WUSAコマンドでインストールしようとしたりすると、「ERROR_BAD_PATHNAME」というエラーメッセージが表示され、処理が失敗するというものです。
.msuファイルは、オフライン環境のPCに更新を適用したり、特定のパッチを選択的に配布したりする際に利用されます。
一般の個人ユーザーがWindows Updateの設定画面からアップデートを行う際にはこの仕組みは使われないため、ほとんどの人には全く影響がない不具合と言えます。
万が一、職場の環境などでこの問題に遭遇した場合は、以下の公式に示されている回避策が有効です。
WUSAアップデート失敗の回避策
最も簡単で確実な回避策は、ネットワーク共有上にある目的の.msuファイルを、一度アップデートを適用したいPCのローカルフォルダ(デスクトップやドキュメントフォルダなど)にコピーし、そこから実行することです。
ローカルのディスクにファイルが一つだけある状態であれば、このパス名に関する問題は発生しません。
Microsoftはこの問題に対して「既知の問題のロールバック(KIR)」という仕組みで対応を進めており、管理されていない多くのデバイスでは、この問題は自動的に解決されると発表しています。
その他に報告されている不具合
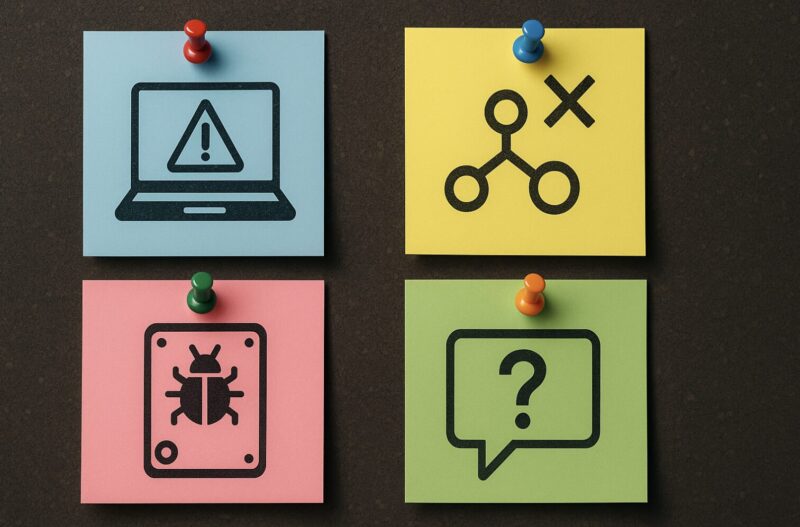
上記の2つの主要な問題以外にも、いくつかの限定的な状況で発生する可能性がある細かい不具合が確認されています。
ご自身のPC環境が該当しないか、念のため確認しておきましょう。
SMBv1プロトコル接続の問題
非常に古いファイル共有プロトコルである「SMBv1」を何らかの理由で有効にしている環境で、古いNAS(ネットワーク接続ストレージ)やWindows Server 2003以前のサーバー上の共有フォルダに接続できなくなる場合があります。
SMBv1は、かつて世界中で猛威を振るったランサムウェア「WannaCry」に悪用された深刻な脆弱性があることから現在は非推奨となっており、Windows 11ではデフォルトで無効化されています。
そのため、近年のPCやネットワーク機器で構成された、ほとんどのモダンな環境では影響はありません。
もし古い機器との接続のために意図的にSMBv1を有効にしている場合は、アップデート後に接続を確認し、可能であればより安全なSMBv2以降への移行を検討する必要があります。
Arm64版PCでのメディア作成ツールの問題
Surface Pro 9 with 5GやSurface Pro Xなど、Arm64プロセッサを搭載した一部のPCで、Windows 11のインストール用USBメモリやDVDを作成するための「メディア作成ツール」が正常に動作しない場合があります。
「PC でこのツールを実行することはできません」といったエラーが表示されることがあるようです。
ただし、このツールは通常、IntelやAMDのプロセッサ(x64)を搭載した一般的なPCで、別のPC用のインストールメディアを作成するために使われることが多いため、こちらも影響範囲は非常に限定的です。
バージョン24H2からの変更は小規模

今回のバージョン25H2アップデートの最大の特徴は、ユーザーからは見えにくい部分ですが、OSの根幹を成すコアシステムがバージョン24H2と完全に共通であるという点です。
そのため、ユーザーが体感できるような華やかな新機能の追加はほとんどありません。
これは「イネーブルメントパッケージ(eKB: enablement package)」と呼ばれる、非常に軽量なパッチによって実現されています。
これは、例えるなら「施錠された部屋の鍵」のようなものです。
新機能のプログラム本体は、実は過去数ヶ月間の月例アップデートを通じて既にPC内に配信・設置済み(施錠された部屋)であり、今回のアップデートはそれらの機能を「有効化(enable)」するための小さな「鍵(eKB)」を送るだけの処理となります。
この方式により、ユーザーには大きなメリットがもたらされます。
イネーブルメントパッケージのメリット
バージョン24H2を実行しているPCであれば、アップデートのダウンロードサイズが非常に小さく(数百KB程度)、インストールにかかる時間も数分程度の再起動1回で完了します。
従来の大型アップデートのように、何十分もPCが使えなくなるような長時間の待ち時間から解放されます。
これは「アップデート疲れ」を軽減し、常に最新の状態を保ちやすくするためのMicrosoftの工夫と言えるでしょう。
言ってしまえば、バージョン25H2は安定性の向上や、水面下でのセキュリティ強化といった、内部的な改善がメインの「メンテナンスアップデート」と捉えるのが最も適切です。
今回のアップデート概要

ここで、Windows 11 バージョン25H2(公式名称:Windows 11 2025 Update)の基本的な情報を表に整理しておきましょう。
ユーザーにとって最も実利的なメリットは、このアップデートを適用することで、お使いのWindows 11のサポート期間がリセットされ、新たに起算される点です。
サポート期間が終了すると、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなり、PCを安全な状態で利用し続けることが困難になります。
特に企業や教育機関のIT管理者にとっては、管理下にある多数のデバイスのライフサイクルを計画する上で、このサポート期間は極めて重要な指標となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公式名称 | Windows 11 2025 Update |
| バージョン | 25H2 |
| OSビルド | 26200 |
| サポート期間(Home/Pro) | リリース日(2025年10月1日)から24ヶ月間 |
| サポート期間(Enterprise/Education) | リリース日(2025年10月1日)から36ヶ月間 |
| 主な変更点 | 内部的な品質向上、セキュリティ強化、サポート期間のリセット |
Windows 11 バージョン25H2の不具合と更新の判断
- 今すぐアップグレードすべきか
- 安全に利用するため更新を待つべきか
- アップデートのダウンロード方法
- アップデートは強制的に更新される?
- Windows 11 バージョン25H2の不具合の総まとめ
今すぐアップグレードすべきか

既知の不具合の報告を見るとアップデートに躊躇するかもしれませんが、それを上回る重要なメリットも存在します。
特に、以下のような考えを持つ方にとっては、早期のアップグレードが推奨されます。
第一に、PCのセキュリティを最優先に考える方です。
バージョン25H2には、単に最新のセキュリティパッチが含まれているだけでなく、OSの「攻撃対象領域(アタックサーフェス)」を削減するための重要な変更が含まれています。
具体的には、古い「PowerShell 2.0」や「WMIC」といった、現在ではより安全な代替手段が存在するものの、攻撃者に悪用されるリスクもあったレガシーな機能がOSから削除されました。
こうした地道な改善は、OS全体の堅牢性を高める上で非常に重要です。
また、前述の通りサポート期間がリセットされることで、今後2年以上にわたって安全な状態でPCを使い続けることが保証されます。
第二に、将来的に提供されるWindowsの新機能をいち早く試したい方です。
Microsoftは近年、「継続的イノベーション」というモデルを推進しており、準備が整った新機能から順次、月例アップデートなどを通じて提供していく方針を取っています。
バージョン25H2は、それらの新機能を受け入れるための最新の「土台」となります。
この土台を整えておくことで、今後数ヶ月のうちに提供されるであろう新しいUIの改善や新機能を、誰よりも早くスムーズに受け取れる可能性が高まります。
私であれば、メインで使っている仕事用のPCでなければ、既知の不具合が自身の使い方に直接影響しないことを確認した上で、早期にアップデートを適用します。
特に、サポート期間が新たに2年間確保されるという安心感は、精神的なメリットとしても非常に大きいですね。
安全に利用するため更新を待つべきか

一方で、アップデートを急がず、少し様子を見るべき慎重なアプローチが適しているケースもあります。
特に以下に当てはまる方は、慌てずに状況を見極めることが重要です。
これは「アップデートしない」のではなく、「最適なタイミングでアップデートする」ための戦略です。
最も重要なのは、そのPCを仕事や学業のメインツールとして使っており、業務や課題の遂行に1日の遅れも許容できない方です。
前述の通り、Blu-rayの再生障害など、特定のニッチな使い方で問題が発生する可能性があります。
リリース直後は、まだ表面化していない未知の不具合が見つかる可能性もゼロではありません。
そのため、最低でも2週間~1ヶ月ほど待って、世の中の評判や追加の修正情報(累積更新プログラム)が出てからアップデートする方が、予期せぬトラブルに遭遇するリスクを格段に下げることができます。
また、お使いのPCのWindows Update画面に25H2へのアップデート通知がなかなか表示されない場合も、無理に手動で適用するのは避けるべきです。
Microsoftは「セーフガードホールド」という仕組みを導入しています。
これは、特定のグラフィックドライバや、特定のアンチウイルスソフト、業務用の特殊なアプリケーションなどとの間に互換性問題が確認されたデバイスに対し、問題が解決されるまでアップデートの配信を自動的に一時停止する安全装置です。
通知が来ないのは、MicrosoftがあなたのPC環境をデータに基づいて保護してくれている証拠である可能性が高いのです。
アップデートのダウンロード方法

アップデートを決意した場合、最も安全で推奨される方法は、Windowsの標準機能であるWindows Updateを利用することです。以下の手順で確認・実行できます。
推奨:Windows Update経由でのアップデート
- 「スタート」メニューから「設定」アプリを開き、「Windows Update」のセクションを選択します。
- 画面の上部にある「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」のトグルスイッチをオン(有効)にします。これをオンにしておくことで、お使いのPCが配信対象となった際に優先的に通知が届きます。
- 「更新プログラムのチェック」ボタンをクリックします。
- お使いのデバイスへの配信が開始されていれば、「Windows 11、バージョン 25H2 が利用可能です。」といったメッセージが表示されます。その下にある「ダウンロードとインストール」ボタンをクリックしてプロセスを開始します。
この方法であれば、ダウンロードはバックグラウンドで行われ、PCの再起動が必要になった際も、ご自身の都合の良いタイミング(例えば夜間や作業の合間)を選択できるため、作業が意図せず中断される心配はありません。
上級者向け:手動でのアップデート(注意点あり)
Windows Updateに表示されるのを待てない場合は、Microsoftの公式サイトから「インストールアシスタント」や「メディア作成ツール」をダウンロードして手動でアップデートすることも可能です。
しかし、これらの方法は前述のセーフガードホールドを強制的に回避してしまうリスクがあります。
実行前には必ず、ドキュメント、写真、各種設定ファイルなど、失いたくない重要なデータの完全なバックアップを外付けHDDやクラウドストレージに作成してください。
特にバージョン23H2以前の古い環境から直接アップデートする場合は、OSのフルインストールに近い処理となるため、時間がかかり、予期せぬトラブルの可能性も高まる点に注意が必要です。
アップデートは強制的に更新される?

「ある日突然、知らないうちにアップデートが始まってしまうのでは?」と心配される方もいますが、その点については基本的に安心してください。
バージョン25H2のような年に一度の機能更新プログラム(Feature Update)は、ユーザーがWindows Update画面で明示的に「ダウンロードとインストール」のボタンをクリックしない限り、自動でインストールが開始されることはありません。
準備が完了しても、最終的なインストールと再起動のタイミングはユーザー自身が指定できます。
ただし、このルールには一つだけ例外があります。
それは、現在お使いのWindows 11のバージョンが、サポート終了期限(End of Service)に近づいた場合です。
サポートが終了したOSを使い続けることはセキュリティ上非常に危険なため、Microsoftはデバイスを安全な状態に保つ目的で、サポート終了の数ヶ月前から、半ば強制的に後継バージョンへのアップデートを開始する場合があります。
とはいえ、今回の25H2がリリースされた直後の段階で、お使いのPCが即座に強制更新の対象となることはまずありませんので、ご自身のタイミングで落ち着いてアップデートを計画してください。


