こんにちは!パソマス Lab運営者のYoshiです。
HPのノートパソコン、スタイリッシュで高性能なモデルも多くて魅力的ですよね。
ですが、検索で「HPのキーボードが使いにくい」と調べてここにたどり着いた方も多いかもしれません。
キーボードの記号が違う配列で入力されたり、特定の文字が数字になる現象に困っていたり、あるいはF1などのファンクションキーが効かない、押すとビープ音が鳴る、なんて症状はありませんか?
また、設定というより「Enterキーが小さい」「小指が打ちにくい」といった物理的な配列や打鍵感にストレスを感じている方もいらっしゃるかも。
キー操作で意図せずカーソルが動くなんてトラブルもあるようです。
これらの「使いにくさ」は、実は簡単な設定ミスからHP独自の設計思想まで、原因がいくつかあります。
この記事では、それらの問題を切り分け、今日から試せる具体的な解決策をステップバイステップでご紹介していきますね。
HPのキーボードが使いにくい原因は設定ミスか?
- 記号が違う?日本語レイアウトの確認
- 文字が数字になるNumLockを解除
- F1が効かないFn Lockの切り替え
- ビープ音が鳴る固定キー機能オフ
- キーでカーソルが動くマウスキー設定
- 反応しない、ベタつくキーの掃除法
記号が違う?日本語レイアウトの確認

「@(アットマーク)」を打とうとしたのに「[」(左角かっこ)になったり、「(」(かっこ)を打ちたいのに「*」(アスタリスク)になったり…。
キーボードのキートップに印刷されている記号と、実際に入力される記号が違うという症状ですね。
これは、Windowsがキーボードを「英語配列 (101/102キー)」として誤認識している可能性が非常に高いです。
私たちは「日本語配列 (106/109キー)」のキーボードを使っているのに、OS側が違う認識をしているために起こるズレなんです。
特にPCの初期設定時や、大きなWindowsアップデート、あるいは外付けキーボードを抜き差しした拍子に設定が変わってしまうことがあります。
Windows 11での確認・修正手順
- スタートメニューの「設定」(歯車アイコン)を開きます。
- 左側のメニューから「時刻と言語」を選び、「言語と地域」をクリックします。
- 「優先する言語」セクションにある「日本語」の右側の「…」(オプション)をクリックし、「言語のオプション」に進みます。
- ページを下にスクロールし、「キーボード」セクションにある「キーボード レイアウト」を確認します。
- ここがもし「日本語キーボード (106/109 キー)」以外(例: 「英語キーボード (101/102 キー)」)になっていたら、それが原因です。
- 「レイアウトを変更する」ボタンをクリックし、プルダウンメニューから「日本語キーボード (106/109 キー)」を選択して「OK」を押します。
- 設定を反映させるために、PCの再起動を求められるので、再起動してください。
これで、キーの刻印通りに記号が正しく入力されるようになるはずです。
まずはここを一番に疑ってみてくださいね。
文字が数字になるNumLockを解除
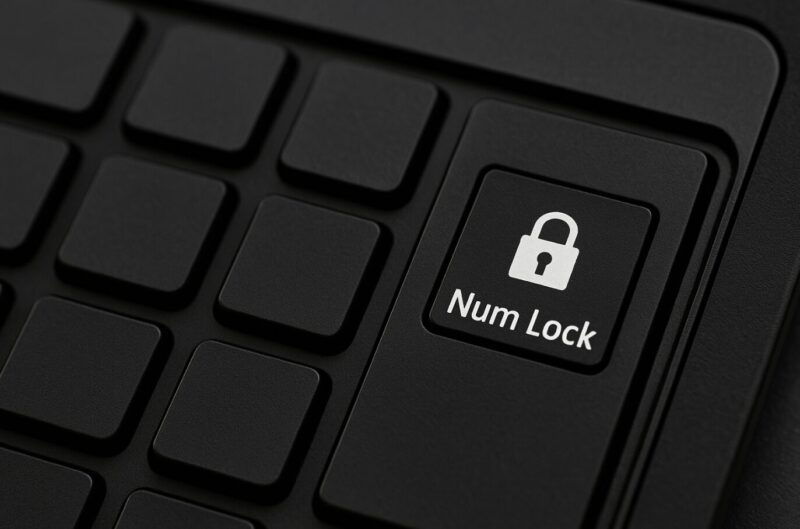
「さっきまで普通に打てていたのに、急に『J』『K』『L』キーを押すと『1』『2』『3』といった数字が入力されてしまう!」…。
これもノートPC特有の「あるある」なトラブルです。
これは「NumLock(ナムロック)」機能が有効になっている証拠ですね。
多くのノートPCには、デスクトップ用のキーボードにあるような「テンキー(数字専用キー)」がありません。
その代わりに、キーボードの一部(主に「U」「I」「O」「J」「K」「L」「M」あたり)をテンキーとして機能させるのがNumLockモードです。
意図せずこのモードがオンになってしまうと、文字を打っているつもりが数字だらけになってしまいます。
どうやって解除する?
解決策はシンプルで、[NumLock] キー(または[NumLk]と表記)を押してオフにするだけです。
ただし、HPのモデルによっては専用の[NumLock]キーが見当たらない場合があります。
その場合、他のキー(例えば[Insert]キー、[F10]キー、[ScrLk]キーなど)に、[Fn]キーと同時に押すことで機能するよう、青や白の文字で小さく[NumLock]と書かれていることが多いです。
[Fn]キー + [NumLock] と書かれたキー
これを同時に押すことで、NumLockモードのオン・オフが切り替わるはずですよ。
メモ帳などで「jump」と打ってみて「140*」のように表示されるか、「jump」とそのまま表示されるかで、モードが切り替わったか確認できます。
F1が効かないFn Lockの切り替え

F1からF12までのファンクションキー。
例えば、F5でブラウザを更新したり、F7でカタカナ変換したり、F10で半角英数にしたり…と、多用する方も多いと思います。
ところが、HPのノートPCでF5を押したら、ブラウザが更新される代わりに「画面が暗く」なったり、F2を押したら「音量」が変わったり…。
これは故障ではなく、「Fn Lock(ファンクションキーロック)」と呼ばれる機能が原因です。
最近のノートPCは、「メディアキー(音量・明るさ調整、再生/停止など)」の操作を優先する設定(ホットキーモード)がデフォルトになっていることが多いんです。
この状態だと、F1〜F12キーは[Fn]キーを押しながらでないと機能しません。
解決策:Fn Lockを切り替える
これを元に戻す(F1キーを単体で押したらF1として機能させる)には、Fn Lockを切り替える必要があります。
多くのHP製ノートPCでは、[Fn]キーと、[Fn Lock]と書かれたキー(または鍵マークがついた[Esc]キーや[Shift]キー)を同時に押すことで、このモードを切り替えることができます。
補足:BIOSで恒久的に設定変更も可能
「PCを起動するたびに設定が戻ってしまう」という場合は、PCの根本的な設定であるBIOS(UEFI)で、このファンクションキーの動作([Action Keys Mode]などと呼ばれます)を恒久的に変更できる場合があります。
ただし、BIOS設定は少し高度な操作になるため、自信がない場合は無理に触らず、まずは[Fn] + [Fn Lock]キーでの切り替えを試すのがおすすめです。
ビープ音が鳴る固定キー機能オフ
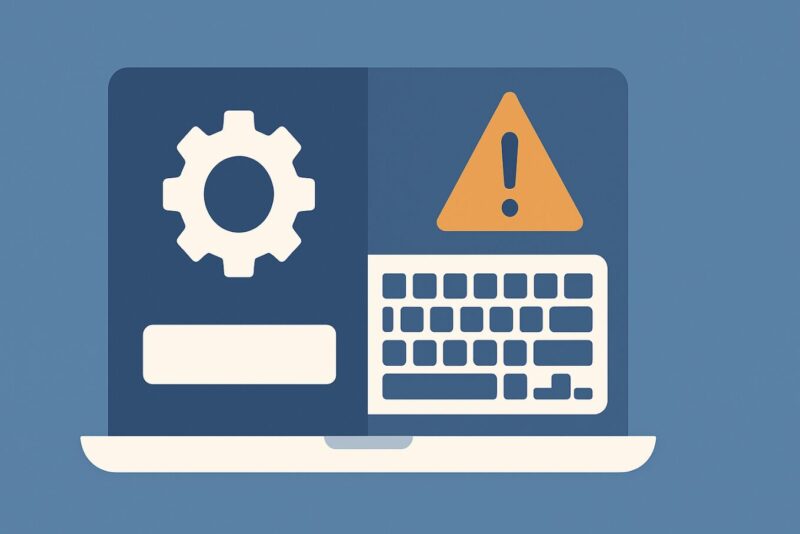
キーを押すたびに「ピッ」とか「ピー」といった、ちょっと不安になるようなビープ音が鳴る場合。これもWindowsの機能が原因であることがほとんどです。
具体的には、Windowsの「アクセシビリティ機能」である「固定キー機能」または「切り替えキー機能」が、意図せず有効になってしまった場合に発生します。
なぜ勝手にオンになる?
これらの機能は、例えば[Shift]キーを5回連続で押したり、[NumLock]キーを5秒間長押ししたりすると、「この機能をオンにしますか?」というポップアップが表示されるように初期設定されています。
ゲーム中や作業に夢中になっているとき、知らずにこのショートカット操作をしてしまい、表示されたポップアップをよく読まずに「はい」を押してしまうと、意図せず機能がオンになってしまうわけですね。
Windows 11での確認・停止手順
- 「設定」アプリを開きます。
- 左側のメニューから「アクセシビリティ」を選び、「キーボード」をクリックします(「操作」セクションにあります)。
- 「固定キー機能」や「切り替えキー機能」のトグルボタンが「オン」になっていたら、それをクリックして「オフ」にしましょう。
今後、勝手にオンになるのを防ぎたい場合は、各機能の設定詳細ページ(「固定キー機能」の右矢印をクリック)に入り、「固定キー機能のキーボード ショートカット」をオフにしておくと安心です。
キーでカーソルが動くマウスキー設定

「キーボードの特定のキー(主にテンキーに相当する部分)を押すと、文字が入力されずにマウスポインター(カーソル)が動いてしまう」。
これは、その名の通り「マウスキー機能」がオンになっているのが原因です。
これもWindowsのアクセシビリティ機能の一つで、マウスが故障などで使えない状況でも、キーボード(主にテンキー)でポインター操作を代行できるようにするためのものです。
NumLockがオンの状態で、意図せずこの機能を有効化してしまうと、この症状が発生します。
解決策は簡単で、タスクバーの検索ボックスで「マウスキー」と検索し、設定画面(「マウス キーパッドでマウス ポインターを移動する」など)を開き、この機能のトグルボタンを「オフ」にするだけです。
反応しない、ベタつくキーの掃除法

「特定のキー(例:『A』キーだけ)が反応しない、または強く押さないと反応しない」「キーを押した感触が『ベタつく』『戻りが悪い』」…。
これは、これまで紹介したソフトウェアの設定ミスではなく、物理的な問題である可能性が高いです。
具体的には、キーの下(キーキャップと本体の間)に、ホコリ、髪の毛、お菓子のカス、あるいはこぼした飲み物(ジュースやコーヒーなど)が溜まっていることが原因です。
ステップ1:エアダスターでの清掃
まずはPCの電源を完全にオフにします(可能ならバッテリーも外します)。
その上で、エアダスターを使い、キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを吹き飛ばしましょう。
ノートPCを傾けながら、色々な角度から噴射するのがコツです。
ステップ2:無水エタノールでの拭き取り
ベタつきの原因がジュースなどの場合、エアダスターだけでは取れません。
綿棒や柔らかい布に「無水エタノール」または「OA機器用クリーナー」を少量染み込ませ、キーの隙間やキーキャップの表面を優しく拭き取ります。(アルコール類はPCの素材を傷める可能性があるので、目立たない場所で試してから、自己責任でお願いしますね)
最終手段:キーキャップの取り外しは自己責任で
それでも改善しない場合、キーキャップを外して内部を直接清掃する方法もあります。
しかし、ノートPCのキーボード(パンタグラフ式)は非常にデリケートです。
キーキャップを外す際にツメを折ってしまったり、内部のパンタグラフ機構を破損させてしまったり、元に戻せなくなったりするリスクが非常に高いです。
もし挑戦する場合は、必ずPCの電源を切り、作業前にキー配列の写真を撮っておきましょう。
特にShiftキーやスペースバーのような大きなキーは、内部に金属バー(スタビライザー)があるため、絶対に触らない方が無難です。
自信がない場合は、無理をしないことを強くおすすめします。
ステップ3:ドライバとBIOSの確認
清掃しても直らない、またはキーボード全体が反応しない、といった場合は、より深刻な問題かもしれません。
HPのPCにプリインストールされている「HP Support Assistant」というツールを使って、キーボードのドライバやPC本体のBIOSが最新の状態になっているか確認し、更新してみてください。
それでもダメな場合は、ハードウェア(キーボード自体やマザーボードとの接続部)の故障の可能性が濃厚です。
HPの公式サポートに連絡し、修理を相談することを検討しましょう。
HPのキーボードが使いにくい物理設計の対策
- Enterキーが小さい、魔の右側一列
- 小指が打ちにくい配列と浅い打鍵感
- 邪魔なキーを無効化するリマップ術
- 最終手段は外付けキーボードの導入
- HPのキーボードが使いにくい問題の解決策まとめ
Enterキーが小さい、魔の右側一列

HPのノートPC(特にEnvy、Spectre、Pavilionといったコンシューマー向けモデル)で、最も「使いにくい」と批判される原因がこれではないでしょうか。
標準的な日本語配列のキーボードでは、EnterキーやBackspaceキーは「キーボードの右端」に位置しているのが普通です。
私たちは、小指を伸ばせば「右端」にEnterがある、と指が覚えていますよね。
ところが、HPの特定のモデルでは、Enterキーのすぐ右隣に「home」「pg up」「pg down」「end」「delete」といったキーが縦一列に配置されているのです。
私はこれを「魔の右側一列」と呼んでいます。
これがタイピング中にどんな悲劇を生むか…もうお分かりですよね。
Enterキーを押したつもりが「Home」キーに当たり、カーソルが意図せず文頭に飛んで、それまで打っていた文章が台無しに…。「ああ、またやった!」と頭を抱えるわけです。
Backspaceを押したつもりが「delete」キーや、モデルによっては「電源キー」を誤打してしまうこともあります。
小指が打ちにくい配列と浅い打鍵感

検索キーワードにもある「小指が打ちにくい」という不満も、この「魔の右側一列」と深く関係しています。
右端だと思って小指を伸ばした先に「壁」ではなく「まだキーがある」ため、タイピングのリズムが崩れ、誤打が頻発し、結果として小指に変な力が入ってしまうんです。
さらに、追い打ちをかけるのが「打鍵感」の問題です。
デザイン性や薄型化を追求するモデル(例:Spectre x360など)では、キーストローク(キーが沈み込む深さ)が1.3mmなど、一般的なノートPC(1.5mm程度)と比較しても浅めに設計されていることがあります。
この浅いストロークと、HP特有のソフトな打鍵感が組み合わさり、「ぺらぺらする」「キーを押した感じがしない」「底打ち感が強くて疲れる」と感じるユーザーが一定数いらっしゃるようです。
モデルによる評価の違い
一方で、法人・プロフェッショナル向けの「EliteBook」シリーズなどでは、キーボードの品質が「秀逸」と高く評価されているモデルも多く存在します。
これは、HPが意図的に「デザイン・薄さ優先のモデル」と「生産性・タイピング優先のモデル」を作り分けている結果だと言えますね。
打鍵感の好みは非常に主観的なので、浅い打鍵感を好む(例:AppleのMagic Keyboardが好き)人もいれば、私のようにしっかりした打鍵感を好む人もいます。
こればっかりは、どちらが良い悪いではないんですよね…
邪魔なキーを無効化するリマップ術

このストレスフルな物理配列問題、もう「慣れる」しかなく、諦めるしかないのでしょうか?
いいえ、ソフトウェアの力でこの物理的な問題を(擬似的に)解決する方法があります。それは「キーリマップ(キー割り当て変更)」です。
要するに、Enterキーの横にある邪魔な「Home」キーを、押しても何も起こらないように「無効化」してしまえばいいわけです。
おすすめツール: Microsoft PowerToys
Microsoftが公式に提供している無料の多機能ユーティリティ「PowerToys」の中に、「Keyboard Manager」という機能が含まれています。
これを使うと、レジストリなどを直接触る危険を冒さず、安全かつ簡単にキーの割り当てを変更できます。(出典:Microsoft PowerToys Keyboard Manager | Microsoft Learn)
具体的な設定例:
PowerToysをインストールして起動し、「Keyboard Manager」で「キーの再マップ」を選択します。そして、以下のように設定します。
- (例1)Homeキーを無効化する
物理キー:「Home」→ マップ先:「Undefined (未定義)」
(これで、誤ってHomeキーを押しても何も起こらなくなります) - (例2)HomeキーもEnterキーにしてしまう
物理キー:「Home」→ マップ先:「Enter」
(これで、Enterの右隣を押してもEnterとして動作するため、実質的にEnterキーが横に広がったのと同じ感覚になります)
これを設定するだけで、「魔の右側一列」によるストレスは劇的に改善されるはずです。
他にも古くから定番の「ChangeKey」といったツールもありますが、PowerToysが一番手軽で安全かなと思います。
※注意点として、キーボードの動作を制御する「Fn」キー自体は、これらのツールではリマップ(無効化)できない点に注意が必要です。
最終手段は外付けキーボードの導入

キーリマップを試してもダメだったり、配列はともかく「打鍵感(浅さ・ソフトさ)」がどうしても自分の体に合わない…という場合。
もう、これが一番確実で、最もストレスフリーになれる最終解決策かもしれません。
それは、好みの「外付けキーボード」を導入することです。
HPのノートPC本体のキーボードは「持ち運び用」と割り切り、デスクでじっくり作業する際は、自分が一番打ちやすいと思うキーボードを接続して使うわけですね。
外付けキーボード選びのポイント
HPのキーボードが不満だったわけですから、選ぶ際は以下の点に注意すると良いかなと思います。
- 配列:
これが最重要です。「魔の右側一列」がない、ごくごく標準的な日本語配列(JIS配列)のモデルを選びましょう。Enterキーが右端にあることを確認してください。 - 打鍵感(キースイッチ):
HPの浅い打鍵感が不満なら、しっかりしたストローク(深さ)のあるものがおすすめです。打鍵感を追求するなら「メカニカル方式」、静音性を重視するなら「メンブレン方式」や「静電容量無接点方式」、あるいは「静音赤軸」などのメカニカルスイッチが候補になりますね。 - 接続方式:
ケーブルの煩わしさがない「ワイヤレス(Bluetoothや専用ドングル)」が人気ですが、安定性や遅延のなさを追求するなら「有線(USB)」もまだまだ現役です。 - サイズ:
数値入力を多用するならテンキー付きの「フルキーボード」、机のスペースを広く使いたいならテンキーのない「テンキーレス」がおすすめです。
HP自身も多くの外付けキーボードを提供していますが、購入する際は「ノートPC本体の配列とは異なる、標準的な配列であること」をよく確認してから選ぶのが重要ですよ。
HPのキーボードが使いにくい問題の解決策まとめ
「HPのキーボードが使いにくい」という、ひとつの検索キーワードの裏には、本当に多様な原因が隠されていましたね。
この記事でご紹介した解決策を、改めてステップでまとめてみます。
「使いにくい」を倒す3ステップ
- Step 1: 設定ミスを疑う(1分で確認)
まずは「記号が違う(レイアウト)」「数字になる(NumLock)」「F1が効かない(Fn Lock)」「ビープ音が鳴る(固定キー)」といった、ソフトウェア側の設定ミスを徹底的にチェックしましょう。 - Step 2: 物理的な問題を疑う(清掃・更新)
特定のキーが「反応しない」「ベタつく」場合は、電源を切り、エアダスターや無水エタノールで慎重に清掃します。また、ドライバやBIOSが最新かどうかも確認します。 - Step 3: 物理設計への対策を講じる(無効化 or 回避)
原因が「魔の右側一列」や「浅い打鍵感」といった物理的な設計にある場合、PowerToysなどのツールで邪魔なキーを「無効化」するか、最終手段として好みの「外付けキーボード」を導入することで回避します。
HPのノートPCは、デザインや性能面で優れたマシンが多いからこそ、キーボードの「使いにくさ」が際立ってしまうのは、本当にもったいないなと私も感じます。
ですが、その「使いにくさ」がどのステップに起因するものなのかを正しく切り分け、適切な対策を講じることで、あなたのタイピング環境は必ず改善できます。
この記事が、HPユーザーの皆さんの生産性向上とストレス軽減に、少しでも役立てば幸いです!


