新しいパソコンを選ぶ際、多くの人が悩むのがメモリ容量です。
特に「パソコンのメモリ8GBは足りないのではないか」という疑問は、多くの方が抱える共通の悩みと言えます。
かつてのWindows10環境では、メモリ8GBでも問題ない場面が多くありましたが、Windows11が主流となった現在、状況は変化しています。
このため、Windows11環境でのメモリ8GBと16GBの比較や、ノートパソコンで8GBが本当に足りるのかという点は、購入前の重要な判断材料となります。
結局のところ、メモリ8GBで十分か、それとも将来を見越してメモリ16GBが必要かという問いに、多くの方が頭を悩ませています。
そもそも8GBメモリでどれくらいの作業ができるのか、具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。
一方で、ノートパソコンにメモリ16GBはいらない、あるいはメモリ16GBは無駄になってしまうのでは、というコスト面での懸念も存在します。
さらに、使い方によってはWindows11ではメモリ16GBですら足りない可能性も指摘されています。
この記事では、結局メモリは8GBと16GBのどちらがいいですか?という根本的な疑問に、様々な角度からお答えします。
あなたの使い方に最適なメモリ容量を見つけ、後悔のないパソコン選びを実現するための、全ての情報をお届けします。
「パソコンの8GBは足りない」と感じる原因と理由
- ノートパソコンで8GBは本当に足りるのか?
- 結局、メモリ8GBで十分か?用途別に解説
- そもそも8GBメモリでどれくらいの作業が可能?
- Windows10でメモリ8GBが足りない場面
- Windows11におけるメモリ8GBと16GBの違い
ノートパソコンで8GBは本当に足りるのか?

ノートパソコンにおいてメモリ8GBで十分かどうかは、その使い方に大きく左右される、というのが実情です。
Webサイトの閲覧やメールの送受信、動画視聴、そしてWordやExcelでの簡単な書類作成といった、比較的負荷の軽い作業が中心であれば、8GBのメモリでもすぐに行き詰まることは少ないかもしれません。
実際、多くの量販店モデルでは今でも8GBが標準的な仕様として販売されており、価格を抑えたい場合には魅力的な選択肢となります。
しかし、現代のパソコン利用環境は、数年前に比べてメモリへの要求を格段に高めています。
例えば、OS自体が高機能化し、Windows 11では起動しているだけで3GBから4GB程度のメモリを消費します。
これに加えて、セキュリティソフトなどの常駐アプリケーションが動作するため、ユーザーが自由に使える領域は最初から限られています。
また、Google Chromeをはじめとする現代のWebブラウザは、利便性や安定性と引き換えに多くのメモリを消費することで知られています。
調べ物などでタブを10個以上開くだけで、ブラウザだけで2GB以上のメモリを使用してしまうことも珍しくありません。
したがって、オンライン会議に参加しながら複数の資料を参照し、同時に議事録を作成するといった、ごく一般的なマルチタスクを行う場面では、8GBのメモリでは動作が著しく遅くなる、いわゆる「もっさり」とした状態に陥りやすくなります。
このため、多くの作業を同時に、かつ快適に行いたいと考えるユーザーにとっては、8GBでは力不足を感じる場面が増えてくる、と言えます。
結局、メモリ8GBで十分か?用途別に解説

メモリ8GBで快適に作業できるかどうかは、パソコンの用途によって明確に分かれます。
自身の使い方と照らし合わせることで、必要なメモリ容量の判断がしやすくなります。
以下の表は、一般的な用途と推奨されるメモリ容量の目安をまとめたものです。
| 用途 | 8GB | 16GB | 32GB以上 |
| Web閲覧、メール、動画視聴 | ○ | ◎ | ◎ |
| Officeソフトでの資料作成 | ○ | ◎ | ◎ |
| オンライン会議と複数アプリ利用 | △ | ◎ | ◎ |
| プログラミング(学習レベル) | ○ | ◎ | ◎ |
| プログラミング(開発、仮想環境) | × | ○ | ◎ |
| 写真編集(RAW現像など) | △ | ◎ | ◎ |
| 簡単な動画編集(フルHD) | △ | ○ | ◎ |
| 高画質な動画編集(4K) | × | △ | ◎ |
| 負荷の軽いPCゲーム | ○ | ◎ | ◎ |
| 最新のPCゲーム、VRゲーム | × | ○ | ◎ |
| ゲーム実況・配信 | × | △ | ◎ |
(◎:非常に快適、○:快適、△:動作はするが遅延あり、×:実用的でない)
8GBで十分な可能性が高い用途
Webサイトの閲覧、YouTubeなどの動画視聴、メールのやり取り、Officeソフト(Word, Excel, PowerPoint)を使った簡単な資料作成といった、一度に一つの作業を中心に行うライトな使い方であれば、8GBのメモリでも大きな支障なく利用できます。
パソコンの利用頻度が低く、複雑な作業をしない方であれば、コストを抑えられる8GBは合理的な選択となり得ます。
16GB以上を強く推奨する用途
一方で、複数のアプリケーションを同時に立ち上げて作業するマルチタスクは、現代のパソコン利用において当たり前になっています。
例えば、ZoomやMicrosoft Teamsでオンライン会議をしながら、Webブラウザで資料を調べ、PowerPointでプレゼン資料を修正するといった使い方では、8GBではメモリ不足に陥り、動作の遅延や不安定さを招く可能性が非常に高いです。
また、写真のRAW現像、動画編集、プログラミング、最新のPCゲームといったクリエイティブな作業や趣味にパソコンを活用したい場合は、16GBが最低ラインと考えられます。
これらの作業は大量のデータを一時的にメモリ上に展開するため、8GBでは処理に膨大な時間がかかったり、アプリケーションが強制終了したりするリスクがあります。
以上のことから、ご自身のパソコンの使い方を具体的にイメージし、それが8GBで対応可能な範囲なのか、それとも16GB以上が必要なレベルなのかを見極めることが、後悔しないパソコン選びの鍵となります。
そもそも8GBメモリでどれくらいの作業が可能?

パソコンのメモリは、よく「作業机の広さ」に例えられます。
メモリ容量が大きければ大きいほど、机が広くなり、たくさんの資料(データやアプリケーション)を一度に広げて効率的に作業できます。
メモリが8GBの場合、この「作業机」の広さは、現代の基準では決して広いとは言えません。
具体的にどのような作業が可能か、イメージしてみましょう。
Windows 11のパソコンを起動した時点で、OS自体が約3GB~4GBのメモリを使用します。
これは、机の上にOSという大きな基本セットが常に置かれている状態です。
つまり、ユーザーが自由に使えるメモリは、最初から残り4GB~5GB程度しかありません。
この状態で、Webブラウザ(Google Chrome)を起動し、タブを1つ開くと約100MB~200MBのメモリが消費されます。
タブを10個開けば、それだけで1GB~2GBのメモリが埋まってしまいます。
これに加えてWordで文書を作成(約500MB)、Excelで表計算(約500MB)を行うと、残りのメモリはかなり少なくなります。
このため、8GBメモリで快適に行える作業は、以下のような単一的なタスクに限られると考えられます。
- Webブラウザのタブを数個程度に抑えたネットサーフィン
- WordまたはExcelのどちらか一方で、複雑な関数や画像を含まない資料の作成
- YouTubeやNetflixなどのストリーミング動画の視聴
逆に、これらの作業を複数同時に行おうとすると、机の上が資料で溢れかえってしまいます。
パソコンは、メモリ(机)に乗り切らないデータを、より低速なストレージ(本棚)に一時的に退避させる「スワップ」という動作を始めます。
この「本棚との頻繁な資料の出し入れ」が、パソコンの動作を著しく遅くする最大の原因です。
したがって、8GBメモリは「一度に一つのことに集中する」スタイルであれば機能しますが、複数の作業を並行して進める現代的な使い方には、対応が難しい容量であると理解しておく必要があります。
Windows10でメモリ8GBが足りない場面

Windows 10が登場した当初、メモリ8GBは「十分な容量」と見なされており、多くのユーザーにとって快適な標準スペックでした。
しかし、時間の経過と共に、同じWindows 10環境であっても8GBでは力不足を感じる場面が増えてきました。
その主な理由は、OSのアップデートとアプリケーションの進化にあります。
Windows 10自体も、リリース当初に比べて機能追加やセキュリティ強化のアップデートを重ねる中で、メモリの消費量は徐々に増加しています。
特に、大型の機能アップデートを適用した後のOSは、より多くのリソースを要求する傾向にあります。
もっと大きな要因は、日常的に使用するアプリケーション側の変化です。
例えば、Microsoft Officeは、クラウド連携や共同編集機能が強化され、昔のバージョンに比べて多機能になった分、メモリ消費も増えています。
Web会議ツールのZoomやMicrosoft Teamsも、パンデミックを経て急速に普及しましたが、これらのツールはビデオ通話や画面共有を行う際に常にメモリを消費し続けます。
また、Webサイト自体もリッチ化しています。
高解像度の画像や動画、インタラクティブな要素が多用されるようになり、Webブラウザがページを表示するために必要なメモリ量も増加の一途をたどっています。
このように、OSは同じWindows 10のままでも、それを取り巻くソフトウェア環境が進化し続けた結果、以前は快適だったはずの8GBメモリのパソコンでも、複数のアプリケーションを同時に起動すると、動作が遅くなったり、応答がなくなったりといった「メモリ不足」の症状が現れる場面が多くなってきたのです。
これは、パソコンの性能が劣化したのではなく、時代の要求にスペックが追いつかなくなった結果と言えます。
Windows11におけるメモリ8GBと16GBの違い

Windows 11環境において、メモリ8GBと16GBのどちらを搭載しているかは、パソコンの快適性に決定的な違いをもたらします。
この差は、単なる数値以上の体感的なパフォーマンスの差として現れます。
OSとアプリケーションの基本動作
まず、Windows 11は公式のシステム要件で最低4GBのメモリを要求していますが、これはあくまで「動作する」ための最低ラインです。
快適な動作のためには、OSだけで4GB近いメモリを消費するため、8GBモデルではユーザーが自由に使える領域は最初から半分以下に限られます。
一方、16GBモデルであれば、OSが消費してもなお12GB程度の広大な空き容量が確保されており、精神的な余裕が全く異なります。
マルチタスク性能
最も大きな違いが現れるのが、複数のアプリケーションを同時に使用するマルチタスクの場面です。
8GBのパソコンでWebブラウザのタブを15個開き、Zoomで会議をしながらWordで議事録を取るといった作業を行うと、物理メモリはほぼ使い切ってしまいます。
こうなると、パソコンは低速なストレージ(SSD/HDD)をメモリの代わりとして使う「仮想メモリ」へのアクセスを頻繁に行います。
これが、アプリケーションの切り替えに数秒待たされたり、ビデオ会議の映像がカクついたりする原因となります。
対して16GBのパソコンであれば、同様の作業を行っても物理メモリにはまだ余裕があります。
仮想メモリへのアクセスを最小限に抑えられるため、アプリケーションの切り替えはスムーズで、全体的な動作も安定しています。
クリエイティブ作業やゲーム
Photoshopでの画像編集やPremiere Proでの動画編集といったクリエイティブな作業では、その差はさらに顕著です。
8GBでは、高解像度のファイルを扱ったり、複数のエフェクトを適用したりすると、処理に非常に時間がかかるか、最悪の場合はアプリケーションがフリーズします。
16GBあれば、これらの作業を実用的な速度でこなすことが可能になります。
同様に、最新のPCゲームの多くは、推奨スペックとして16GBのメモリを要求しています。
8GBでは、ゲームのロード時間が長くなったり、プレイ中にフレームレートが低下してカクついたりする原因となります。
このように、Windows 11においては、8GBと16GBのメモリは「なんとか動く」と「快適に使える」という、根本的なユーザー体験の差を生み出すのです。
パソコンで8GBが足りないなら16GBは必要か
- 結局メモリは8GBと16GBのどちらがいいですか?
- メモリ16GBの必要性を利用シーンから考える
- 本当にメモリ16GBは無駄になってしまうのか
- ノートパソコンにメモリ16GBはいらないのか
- Windows11でメモリ16GBでも足りない?
- 後悔しないために。パソコン8GBが足りない時の結論
結局メモリは8GBと16GBのどちらがいいですか?

パソコンのメモリ容量で「8GBと16GBのどちらが良いか」という問いに対しては、2025年現在の状況を踏まえると、ほとんどのユーザーにとって「16GBが賢明な選択」であると言えます。
その理由は、短期的な快適性と長期的な安心感の両面から説明できます。
まず短期的な快適性です。
前述の通り、現在のOSやアプリケーションは、8GBのメモリではすぐに上限に達してしまうほど多くのリソースを要求します。
Webブラウザで多くのタブを開いたり、オンライン会議に参加したり、Officeソフトを複数使ったりといった、ごく日常的な使い方でさえ、8GBでは動作の遅延や不安定さを感じる場面が増えています。
16GBのメモリを搭載していれば、これらの作業を複数同時に行ってもメモリに余裕が生まれ、ストレスのないサクサクとした動作を維持できます。
この日々の快適さは、作業効率や精神的な満足度に直結します。
次に長期的な安心感です。
パソコンは一度購入すると数年間は使い続ける高価な買い物です。
そして、ソフトウェアは今後も進化を続け、さらに多くのメモリを要求するようになることは間違いありません。
特に、Copilotに代表されるAI機能がOSに標準搭載される流れは、この傾向を加速させるでしょう。
現時点で「ギリギリ足りる」8GBという容量は、2~3年後には「完全に力不足」になっている可能性が極めて高いのです。
購入時に少し予算を追加して16GBを選択しておくことは、将来のソフトウェア環境の変化に対応するための「保険」であり「投資」と考えることができます。
特に、後からメモリ増設ができないノートパソコンの場合は、この購入時の判断が数年間の快適さを決定づけることになります。
もちろん、用途がWeb閲覧やメールなどに完全に限定されており、予算を最優先したいという方であれば8GBも選択肢にはなります。
しかし、少しでも長く、快適にパソコンを使いたいと考えるのであれば、16GBを選ぶ方が結果的にコストパフォーマンスの高い選択になると言えるでしょう。
メモリ16GBの必要性を利用シーンから考える

メモリ16GBの必要性は、特定の利用シーンを想定すると、より明確になります。
8GBでは対応が難しい、あるいは非効率になってしまうものの、16GBあれば快適にこなせる代表的な利用シーンは以下の通りです。
クリエイティブ・プロフェッショナルな作業
- 写真編集(RAW現像): デジタル一眼レフで撮影したRAWデータは、1枚あたり数十MBと非常に巨大です。Adobe Lightroom Classicなどで多数のRAWデータを読み込み、色調補正やノイズリダクションといった処理を行う際には、大量のデータをメモリ上に展開する必要があり、16GBメモリがその快適性を大きく左右します。
- 動画編集: フルHD(1920×1080)解像度の動画編集は、16GBが実用的な最低ラインとなります。複数の動画クリップ、テロップ、BGM、エフェクトを重ねたタイムラインをスムーズにプレビューし、書き出し(エンコード)時間を短縮するためには、十分なメモリ容量が不可欠です。
- グラフィックデザイン・イラスト制作: Adobe PhotoshopやIllustrator、CLIP STUDIO PAINTなどで、多数のレイヤーを使ったり、高解像度のキャンバスで作業したりする場合、16GBメモリがあれば動作のもたつきを抑え、創造的な作業に集中できます。
開発・研究用途
- プログラミング: 複数の開発ツール、エディタ、ブラウザを同時に立ち上げてコーディングを行う場合、16GBあると快適です。特に、Dockerコンテナで仮想的なサーバー環境を複数動かしたり、Android Studioでスマートフォンのエミュレータを起動したりするような場合は、8GBではメモリ不足に陥りがちです。
- 仮想環境の利用: VMwareやParallelsなどの仮想化ソフトを使い、一台のPC上でWindowsとLinuxを同時に動かすといった使い方では、ホストOSとゲストOSそれぞれにメモリを割り当てる必要があります。このようなケースでは16GBメモリが必須となります。
- CADソフトの利用: 建築・機械系の設計で使われるAutoCADなどの3D CADソフトは、複雑なモデルを扱う際に大量のメモリを消費するため、16GB以上の搭載が推奨されています。
快適なエンターテイメント
- 最新PCゲーム: 「Starfield」や「Cyberpunk 2077」といった多くの最新3Dゲームでは、推奨システム要件として16GBのメモリが指定されています。美しいグラフィックを高画質設定で、かつ安定したフレームレートで楽しむためには、16GBはもはや標準的なスペックです。
- ゲーム実況・配信: ゲームをプレイしながら、OBS Studioなどのソフトでその映像をキャプチャし、YouTube LiveやTwitchで配信するといった行為は、PCに極めて高い負荷をかけます。ゲームと配信ソフトの両方がメモリを大量に消費するため、16GB以上のメモリが安定した配信には欠かせません。
これらの利用シーンに一つでも当てはまる、あるいは将来的に挑戦してみたいと考えているのであれば、メモリ16GBは「贅沢品」ではなく「必需品」と言えるでしょう。
本当にメモリ16GBは無駄になってしまうのか

「自分の使い方はWeb閲覧やOfficeソフトが中心だから、16GBも搭載しても性能を持て余して無駄になるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、ライトな使い方であれば、16GBのメモリを常にフル活用する場面は少ないかもしれません。
しかし、結論から言うと、メモリ16GBは決して無駄にはなりません。
むしろ、見えない部分でパソコンの快適性と安定性に大きく貢献しています。
その理由は、WindowsというOSのメモリ管理の仕組みにあります。
Windowsは、利用可能な物理メモリが多ければ多いほど、その領域を積極的に活用してパフォーマンスを向上させようとします。
具体的には、「スーパーフェッチ」や「プレフェッチ」と呼ばれる機能が、ユーザーがよく使うアプリケーションのデータをあらかじめメモリ上に読み込んでおくことで、アプリの起動時間を短縮します。
メモリに余裕があるほど、この先読みの恩恵を大きく受けることができるのです。
また、メモリに十分な空き容量があるということは、前述した低速なストレージをメモリ代わりに使う「スワップ」の発生を極限まで抑えられることを意味します。
スワップはパソコン全体の動作を遅くする最大の要因の一つであり、これを回避できるだけでも体感速度は大きく向上します。
さらに、スワップはSSDへの書き込みを伴うため、その頻度を減らすことは、長期的にはSSDの寿命を延ばすことにも繋がると考えられます。
このように、メモリ16GBは、たとえ使用率のグラフが常に100%に張り付いていなくても、OSによるキャッシュ機能の強化やスワップの抑制を通じて、パソコン全体のレスポンスを向上させています。
さらに、将来性という観点も重要です。
2、3年後には、OSやアプリケーションの要求スペックがさらに上がり、現在の8GBがかつての4GBのような「最低限」の立ち位置になっている可能性は十分にあります。
「あの時16GBにしておけばよかった」と後悔するよりも、未来の快適さへの投資として16GBを選んでおくことは、非常に合理的な判断と言えます。
したがって、メモリ16GBは、ライトユーザーにとっても「持て余す」のではなく、「余裕と安心をもたらす」価値ある選択肢なのです。
ノートパソコンにメモリ16GBはいらないのか

「ノートパソコンは持ち運びがメインで、デスクトップほど負荷の高い作業はしないから、メモリ16GBはいらないのでは?」という意見も一理あります。
しかし、現代のノートパソコン選びにおいては、この考え方が大きな落とし穴になる可能性があります。
その最大の理由は、近年のノートパソコン、特に薄型・軽量モデルの多くで採用されている「オンボードメモリ」という仕様にあります。
かつてのノートパソコンは、本体の裏蓋にある小さなカバーを外すだけで、ユーザー自身が簡単にメモリを交換したり増設したりすることが可能でした。
そのため、「まずは8GBで購入し、将来的に足りなくなったら16GBに増設しよう」という柔軟な対応ができました。
ところが、現在の薄型ノートパソコンでは、本体の極限までの薄型化や軽量化を実現するために、メモリチップがマザーボード(PCのメイン基板)に直接はんだ付けされている「オンボードメモリ」が主流となっています。
このオンボードメモリは、物理的に取り外したり交換したりすることができないため、購入後にメモリ容量を増やすことは一切不可能です。
つまり、ノートパソコンを購入した瞬間に、そのパソコンが寿命を迎えるまでのメモリ容量が確定してしまうのです。
この「後戻りできない」という事実は、ノートパソコンのメモリ選びにおいて極めて重要なポイントです。
購入時点では「8GBで十分」と感じていても、2年後、3年後に自身の使い方やソフトウェア環境が変化し、「やっぱり16GB必要だった」と感じた時には、もう手遅れです。
その場合、動作の遅さに耐えながら使い続けるか、パソコン自体を買い替えるしか選択肢はありません。
このようなリスクを避けるためにも、ノートパソコンこそ、購入時に将来の使い方まで見越して、余裕のある16GBを選択しておくことが強く推奨されます。
数年間の快適性と安心感を確保するための「保険」として、16GBメモリへの投資は非常に価値が高いと言えるでしょう。
もちろん、一部のゲーミングノートやビジネスノートでは増設可能なモデルも存在するため、購入前には必ず製品仕様を確認することが大切です。
Windows11でメモリ16GBでも足りない?
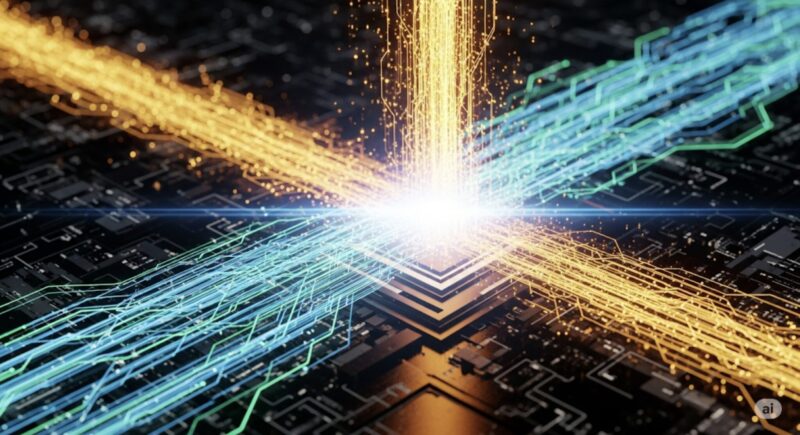
多くのユーザーにとって16GBは快適なメモリ容量ですが、「Windows 11環境では、16GBでも足りない」というケースも、特定のプロフェッショナルな用途においては存在します。
一般ユーザーが心配する必要はあまりありませんが、どのような場合に16GBの壁を超えるのかを知っておくことは、PCの性能限界を理解する上で役立ちます。
16GBメモリが不足する可能性があるのは、主に以下のような極めて負荷の高い作業です。
4K以上の高解像度動画編集
フルHDの動画編集であれば16GBでも対応可能ですが、解像度が4K(3840×2160)や8K(7680×4320)になると、扱うデータ量が爆発的に増加します。
4K動画のクリップを複数重ね、カラーグレーディングや高度なエフェクトを適用し、リアルタイムでプレビューするといった作業では、16GBのメモリは瞬く間に消費され、動作が非常に不安定になります。
こうしたプロの映像制作の現場では、32GBや64GB、あるいはそれ以上のメモリを搭載したワークステーションが標準的に使用されています。
本格的な3DCG・VFX制作
映画やゲームで使われるような、複雑な3DCGモデルやフォトリアルなレンダリング、VFX(視覚効果)の制作も、メモリを大量に消費する作業の代表格です。
多数のポリゴンを持つモデルや、高解像度のテクスチャ、複雑なライティング設定などを扱うには、16GBでは全く足りず、32GB以上が必須となります。
大規模なソフトウェア開発・データサイエンス
数百のコンテナを同時に動かすような大規模なWebアプリケーション開発や、数GBを超える巨大なデータセットを扱う機械学習、ディープラーニングといったデータサイエンスの分野でも、16GBではメモリ不足に陥ります。
モデルのトレーニングや大規模な数値計算には、潤沢なメモリ容量が直接的に処理速度に影響します。
複数の仮想マシンを同時に高負荷で動かす
研究や開発の現場で、複数のOS(例: Windows, Linux, macOS)を仮想マシン上で同時に起動し、それぞれで負荷の高いアプリケーションを実行するような場合も、各仮想マシンに割り当てるメモリを考慮すると、ホストPCには32GB以上のメモリが求められます。
これらの例は非常に専門的であり、ほとんどの一般ユーザーやビジネスユーザーの利用範囲を超えるものです。
したがって、「16GBで足りなくなるかもしれない」という不安を過度に抱く必要はありません。
一般的な用途であれば、16GBは今後数年間にわたって快適な環境を提供してくれる、非常にバランスの取れた容量と言えるでしょう。


